私は所属が立教大学文学部におりまして、専門は地理学、生態人類学というのをやっています。今日は「アート」ということで話をしてくれということで、どうしようと思ってしまいまして、すごく緊張してスーツを着てきてしまったんです。「生きるための昆虫食」ということで、「生きる」ってなんだろうと思いまして、何かタイトルを付けないといけないなと思ってこういう二つの漢字を当ててみた。
人を「ざかざか」させること
この字分かりますかね?「蠢蠱」。「蠢蠱」(しゅんこ)と読みます。春の下に虫がうごめく、「蠢動」という言葉があって、春になって虫がざかざか出てくると。そしてこの「蠱」という字は「蠱毒」という毒があって、中国に伝わっているものでものすごい猛毒だそうです。そういう恐ろしげな字なんですけど、そういうところで虫を食べるとはどういうことなのかということをアートという土台に乗せて今から考えてみたいと思います。みなさんと共にいろいろと議論をしながら話を進めていこうと思っています。基本的にアートというものは「人間が人間であることのひとつ」だと思うんですけど、アートというのが人の感性を動かすということであれば、人をざかざかさせる、ということが重要ではないのか。良い方に行くのか、悪い方に行くのか、どっちにしてもざかざかさせるということで、今日は最初から客席のお皿に昆虫をのっけてみたんですけど、話をする前から結構多くの人がつまんで食べて、美味いと言ったり、まだ手を出せないという人がいたり。今日の目標としては手を出せないという人に、出してみよう、という気にさせるかどうかということでもあり、逆にやっぱりアートというのはこだわりでもあるので、俺は絶対食べないぞ、私はこんなものは嫌だ、という確信をさらに強く持っていただくということもあってもいいのかなと思っております。
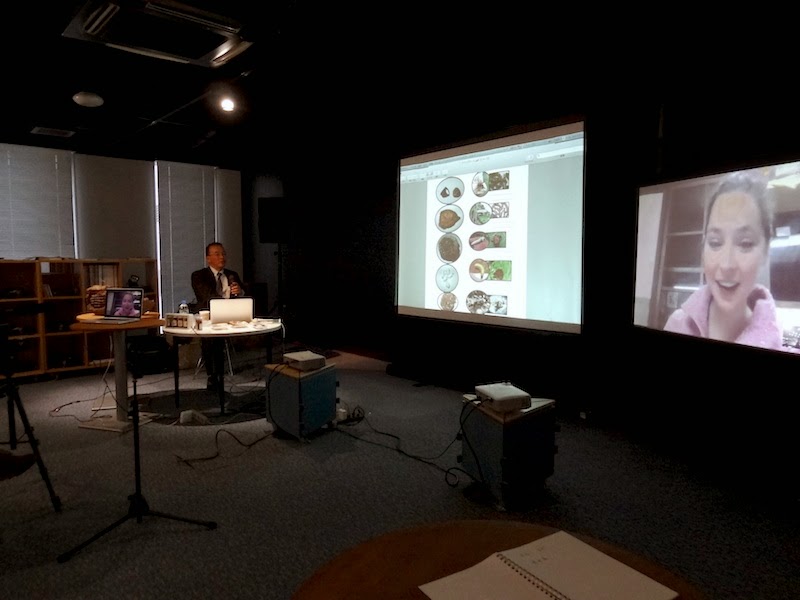
虫を食べる「人」の研究
おおかたの昆虫を食べている人は「現代社会」のことを考えていません。「好きだから食べている」ということを強く訴えたい。虫を食べる人、その「人」がなんたるものか。だからわたしも文学部にいて、食べる「虫」の研究ではなくて、虫を食べる「人」を調べているんです。昆虫食を基軸に、人と自然との関係のあり方、どのように自然環境と交流するのか、まさに私がやっているのはこういうことなんです。そして今、ヨーロッパのほうで昆虫食が注目されているわけです。これからまだまだ人口が増加するという中で、虫を食べると人類が救われる、みたいなことが世界的に流れました。FAO(国際連合食糧農業機関)がそういうことを言ったということで、昆虫食が一気に脚光を浴びるようになりました。私もこの会議に出ているんですけど、「何か違うな」というところがありまして、まずはFAOが何を言っているかということを紹介したいと思います。世界では虫は1900種以上食べられていると言われています。もっと多いと思いますけど、とにかく食べている。世界の今20億人が虫を食べているんだから、もっと虫も食べれるぞと。何が良いかという話なんですけど、家畜と比べたとき、飼育面積が圧倒的に少なくても同量のエネルギーを得ることができる、というものです。蚕は何段にも積み上げて飼うことができる。牛はなかなか高層ビルで飼うことは難しい。次に温室効果ガスで、生き物は生きていく上で二酸化炭素等を出します。虫が出す量は少ない。これも得られるエネルギーに対して非常に効率が良いということが言われ、地球温暖化にも効果があると言われています。もうひとつは、虫を養殖した場合にかかる餌のコストですね。牛を育てるのにはけっこうな草、肥料が要ります。それに比べて虫は少しでよいと。同じ10キロの餌があれば、牛は1キロしか作れないけど、虫は9キロ作れるよと。環境によい、健康にも経済にも良い、ということで昆虫食をもっと進めていこうではないかということで、進んでいるわけです。
創造とは「現実を知る」そして「想像する」こと
そういうところで、今日のもうひとつのお題、「創造」ということを考えてみる。虫は効率がいいから食べろ食べろと言われて、それで食べても全然創造的でも何でもなくてですね、いいようにやられてしまうという感がある。「生きるために」とFAOが言うように、人口が増えていく、だから虫などのエネルギー効率が良いものを食べなさい、と。まさにサバイバルですね。あるいはフィード(餌やり)。そういうために食べるものなんだろうか?さきほど「美味しいから食べる」と非常に良いことをおっしゃっていただいて、今日はいかに虫が美味しいかということを考えていこうと思うわけです。それでは虫が美味しく見えるか、見えないのかということですけども、美味しいというのはやっぱり誰にでも共通するものではないと思います。人によって美味しいものは違う、それは当たり前のことです。食べるもの、食べられないものに、絶対的なものはない。そこで重要なのは、人が人として生きるために、いかに満足するか、幸せになるかというところにあるかと思います。そういう美味しいものを見つけていく、探していくというところにひとつの創造がある。それを自然、つまり自分たちが作ったものではない環境から、外から得るというところに創造性がどう働くか、ということだと思います。創造(クリエイト)というところへ行くとき、まず「現実を知る」ということ、それと「想像(イマジン)する」という二つから、見えてくるんだろうと思います。創造するためには、いろいろなことを知らなければ想像できない。それがあった上で始めて新しいものを作っていくことができる。
人と自然との関係ということですけど、私たちが何か食べ物をとるというとき、ほとんどは自然のもの、生き物です。そのように自然と必ず関わってくるというのが食べ物の世界です。そこで「生き物」から「食べ物」にする、というところにひとつ創造の見所があるのではないかと考えます。食べ物と言っても、それを食べ物と見做すかどうかですね。みなさんの目の前に置かれたイモムシを見てこれを食べれるかどうかということがあったかと思いますけど、それは食べるという発想を持つことがあって初めて食べ物になるわけです。ではそこにあるためにはどうするのか、取ってこなければいけないわけです。そのためには虫はどこにいるか、いついるか、知らなきゃいけません。おおかたの生き物は生きていくために必死です。逃げていきます。それをいかにして捕まえるかということですね。そのための知識、技術というのが必要です。それで、取ってきて、どうするか?生でばくばく食べているだけではないのです。どうやって美味しく食べるか、あるいは食べられないものを食べられるようにするか、というのもあります。そのためには昆虫に近づく、取ってくる、食べる、ということになりますが、なかなか一人でやれるものではない。社会の中で、知識を共有する、受け継いでいく、一緒に取りに行く、一緒に料理する、一緒に食べるということがありますんで、お互いに分かっているという関係作り、コミュニケーションというのも必要になってきます。環境の中で虫がどういう位置にあるのか、どういうふうに出現するのかという状況と、人間側の社会、知識、あるいは美味しいということに対する価値観、そういう情報が合わさって昆虫食というものが成り立っているということになります。
これはどこでも同じものではなくて、土地によって違う、民族によって違う、地域によって違うということになっていきます。多様性があり、多様性を理解することで、そんな虫を食べるのか、そんなやり方があるのか、ということも理解できるのかなと思います。虫を食べないのもひとつの選択ですが、食べることを選択するとき、単純にそこに虫がいるから手に取る、というわけにはいかない。様々な条件があってそれが可能になる。その条件を明らかにしていくことが重要だと思います。すべての虫を食べるというのではなく、そこには選択があります。食用の昆虫種1900種と申しましたが、昆虫の種類自体はもっとたくさんの種類がいて、1900種はそのうちのごく一部であり、きちんと選択した結果、取りやすかったり、条件を満たすものが選ばれてきているわけです。虫を食べると言うと、「他に食べるものがないから食べているんだろう」と言われてきました。さらに「山のほうの貴重なタンパク源だから」などとも言われてきましたが、本当にそうでしょうか?虫だけ食べて生きることはできません。それはあくまでも食生活の一部であり、その一部に虫を選ぶセンスというものも面白い。ひとつの虫を食べるということは大変なんだということを考えたい。

生きるとは「執念」と「情熱」
カメムシは日本では、稲について、ちょうどこれから実を熟していこうというときに汁を吸う。そうすると稲のほうがダメージを受けて、米が実った頃に大きな斑点ができる「黒斑病」にかかってしまう。そうなると米が売れない。1000粒中6粒混じっているともう商品にならないので、そのために農薬を撒く。ネオニコチノイド系農薬というのが問題になってきていて、ヨーロッパのほうでは使用しないような動きになっています。そういうカメムシなんですが、ラオスではこれも串焼きにして食べてしまう。この作り方なんですが、カメムシは冬場に集まって越冬します。これを女性たちが取ってきます。これはくさいので、生きた状態で茹でます。茹でる前に殺しちゃだめなんです。生きた状態で入れると向こうも怒ってくさいのを出します。これを天日乾燥させて出来上がり、すごい努力ですね。生きるため、サバイバルのためにこれを食っているわけではないんですね。くさいのを我慢して、生きるために食べるのではなく、美味しく食べるためなんです。
ものによってはリンゴのにおいのするカメムシとかもいるんですけど、もともとは自分でくさいにおいを作り出しているのではなくて、草に含まれているのを集めていった結果こういうものになる。カメムシがそれをあえて集めて、自分を守るためのにおいにしたというのは、すごい偉いやつだと思うんですが、これを食べれるようにした「人」というのもさらに偉いですね。とにかく美味しく食べたい、と。実際にこれ、食べると美味しいんです。ナッツのようで、脂肪分も多い。生きるということは何か?自分なりにこの数日で考えた結論は、「執念」と「情熱」ということですね。これはきっとアートだろうと。特性を見出す、思考する、生かす技術、食べるための障害を取り除く努力をする。ラオスではどうやら焼くことによってにおいを飛ばしているんですけど、これを唐辛子と混ぜて搗いて、ペースト状のもの(チェオ)を作る。生きた状態でいっちゃう。田んぼに行って生きているやつをそのまま捕まえて食べている。ということでわたしもチャレンジしてみました。食べると、本当に、口の中にそのにおいがわーっと広がっていって、嫌だな、と思ったんですが、その「嫌だな」というのが数秒でふっと飛んでしまいます。揮発性が高いのか、慣れてしまうのか、そこは微妙なところなんですが、においを感じなくなってしまった後に、カメムシのすごく美味しい味がわーっと広がるんですね。美味しさが脳内を駆け巡り、頭の中に花が咲き乱れるという感じですね。しかも害虫退治になる。
「際」(きわ)の重要性と複合的な価値
ラオスも日本と同じように水田を作っています。ただここは天水田という、灌漑をしていない雨水だけの田んぼです。(スライド)これはコオロギをどこで取るかトラッキングしていったデータなんですが、田んぼと森との境の部分、「きわ」で取っています。そういう場所のことを生態学的に言うと「エッジ」と言って、森の端から先が開けているので、生物が攪乱状態になっているので、植物種がどんどん変化し多様性を増すということで、餌となるものも多く、様々な生物が住みます。このことを社会に敷衍して考えるのであれば、私たちが合理的にするというのは一般的に、水田を作るときは区画化して、直線的に区切るわけなんですが、がたがたにして「エッジ」をたくさん作るようにすればコオロギがたくさん取れ、米も取れる。多様性を作るということを念頭に入れれば、そういう土地開発をするという発想が生まれるのではないでしょうか。
(スライド)こちらは天水田の乾季真っ只中の風景なんですけど、雨が降らず荒れ地状態です。外の人は、ここで水を引けば米を作れるだろうと言ってきますが、ここに別に何もないわけではありません。フンコロガシがいるんですね。ここのフンコロガシは水牛や象のフンを餌とします。ここでは水牛を使って農耕してました。水牛がいるので、田んぼが終わった後、稲の穂だけ刈り取れば、下の部分は残って、それが水牛のエサになります。それを食べてフンをする。そのフンを求めてフンコロガシがやってきて、その中で幼虫を作る。その幼虫を食べるわけですね。フンというと汚いイメージがあります。フンの中で幼虫は蛹になりますが、蛹になるとき、幼虫は汚いものを全部出して、きれいな身体になって、タンパク質の塊のようになっています。そこを見計らって、取り出して炒めたりシチューにしたりして食べる。そういう知識、すごいなと。
田んぼというのは田んぼだけであるのではなくて、虫も含めて田んぼなんだということです。田んぼという「場」があることによって、いろんな生物の棲息が可能になる。生き物の豊かな営みというものを作り出す場なんです。稲というものはその一部なんだという発想ですね。ラオスでは水を引くための灌漑設備を作るには金がかかる。そして、作った米が売れるかというと、それほど売れず、農家にとってさほど収入にならない。それよりもフンコロガシを取って売るというほうが金になる。近代はいかに合理的にするか、つまり単一、均一、という方向を目指していたが、ここでは「複合性」という見方を作っていけるんじゃないかと思います。最近ヨーロッパで「プルーラル・アクティビティズ」あるいは「プルーラル・サブシステンス」、つまり「複合的な生業」というものが出てきて、それについて具体的にどうしようということをなかなかヨーロッパの人は言えないが、アジアでは具体的にやってきた。ヨーロッパの人はアジアでは当たり前の様になっている「複合的な価値」というものを判断できなかった。むしろそれは近代合理性に反するものとしてネガティブに捉えていたんですが、逆にもっと出していっていいのではないか。「自然と人間」という二つの関係が言われてきたわけですが、その中に生き物の営みがあって、その循環の中にある、稲、水牛、フンコロガシ、人間、の関係。自然と人間との単純な重なりの中には時間と空間というものがあって、そこでいろんな生き物の営みがあって、そこで連鎖が行われている。そこを明らかにしていく、多様性を見出していくということが重要ではないかと思います。昆虫食はいろいろなところで「貧しい故に虫を食べている」と言われるが、実際は虫は高級品として売られ、ごちそうとして食べられている。取るのが大変という中で商い、それを買うといううれしさがあるのではないでしょうか。
恵那市串原のヘボ(クロスズメバチ)
(NHKのドキュメンタリー番組『<夢の地バチが飛んだ>ー岐阜県 串原村ー』の紹介)これはまさに自然との交流を示した素晴らしい作品だと思います。これまではハチは秋に取って食べるというところで終わっていたんですが、90年代頃に串原でハチを越冬させることに成功した。それがテレビ番組で紹介されることによって、あちこちでやってみようという気運が高まって、全国地蜂同好会というものができたんですね。半養殖までできるようになったのは世界的にエポックメイキングなことです。それを成功させた人たち、そしてそれを広げたメディアというのも、すごく面白いと思います。三宅会長は「我がヘボ人生」と題して講演も行いました。串原では毎年11月3日に「ヘボの巣コンテスト」というのをやっています。ここでみんなが半年かけて育てた巣を持ち寄って大きさを競います。大きさを競うだけではなくて、ヘボを使って作った五平餅をみんなで食べます。面白いのは、この場で巣を出すので、働きバチがわんさか舞っています。しかもハチは巣を壊されるので凶暴になっている、という中で、大勢の人が集まってコンテストをやっている。これは岸和田だんじりに並ぶ、世界で一番恐ろしい祭りのひとつではないかと思います。スズメバチに刺されたら死ぬ、みたいな噂も広がってしまっていますけど、刺される中でもみんな見にきている。人の信頼の力というものはすごいなと思います。こういうことを新しくするとなったら、いろんな人が反対して絶対にやらせてもらえません。これは去年で二十回目です。こういうことができる結束力、これも大きな創造だと思います。
細部に宿る創造性
自然と社会のコミュニケーション。先程の三宅さんは自然環境の中でヘボが育つ空間を作ってきた。そこでいろんな人とのコミュニケーションが可能となって、世代がつながっていく。ただ残念なことに全国的に高齢化が進んで、なかなか次の世代につなげていくのは難しいというところですが、それでも若い世代の人たちが次のヘボ祭りをやっていくという宣言をして、続けていって欲しいなというところです。まとめですが、昆虫食とアート、という非常に難しい問題に立ち返ってみますと、昆虫は「虫けら」とまで言われるようなものですが、それを細かく見ていくとき、「そんな瑣末なことを見たところで」という意見が出てきますが、そうした瑣末とか細やかさ、あるいはバラエティに富むところ、そういうものを見ていくと、昆虫食というものが非常に面白いものに見えてくるのではないか。社会の中でこういうことをやらせてもらえるという相互理解とコミュニケーションというものがあって成り立つ世界だということですね。ちっぽけな虫を取るために色々な技術を使う。技術も発達させていっている。未だにハチを取る手法も新しいことが試されて、常にイノベーティブなことをやっているんですね。それは共有され、共有されることによってさらに強められていく、あちらとこちらで工夫の応酬というものが見えてきます。ということで、昆虫食がアートと思っていただけるかどうか。重要なのは、今日、虫を食べてみようか、という勇気ある創造をする人が出るかどうかということですね。ありがとうございました。

